
愛犬のストルバイト結石が治らないと悩んでいませんか?ストルバイト結石は原因を正しく理解し、適切な対策をとることで改善が期待できる病気です。しかし、症状が続いたり再発を繰り返したりする場合、食事管理や生活習慣に問題がある可能性があります。
特に、療法食を与えているのに改善しない場合、療法食はいつまで続けるべきか悩む飼い主も多いでしょう。また、適切なおやつの選び方や、さつまいもなどの食材が影響を与えるのか気になる方もいるはずです。
この記事では、ストルバイト結石が治らない理由と対策について獣医師が詳しく解説します。愛犬の健康を守るために、食事管理や排尿習慣の見直しを行い、再発を防ぐための正しいケアを身につけましょう。
犬のストルバイト結石が治らない原因と対策
ストルバイト結石の主な原因とは?
ストルバイト結石は、犬の尿路に発生する代表的な結石の一つです。結石ができる原因はいくつかありますが、特に尿の性質や生活環境が大きく関係しています。
尿のアルカリ性化
ストルバイト結石は、尿がアルカリ性に傾くことで形成されやすくなります。犬の尿のpHバランスは食事や水分摂取量によって変化し、特にマグネシウムやリンが多く含まれる食事を摂取していると、尿がアルカリ性に偏りやすくなります。
細菌感染による膀胱炎
細菌性膀胱炎もストルバイト結石の大きな原因の一つです。一部の細菌は尿をアルカリ性に変化させる働きを持っており、その結果、結石が作られやすくなります。また、膀胱内で炎症が続くと、尿中のタンパク質や細胞が増え、これらが結石の核となる可能性があります。
水分摂取不足
水を十分に飲まないと尿が濃縮され、結石の形成を助長します。特にドライフード中心の食事をしている犬は、水分摂取量が不足しやすく、膀胱内のミネラル成分が結晶化しやすくなります。
排尿回数の減少
排尿の回数が少ないと、尿が膀胱内に長時間留まり、結晶が集まる時間が増えます。トイレの回数が少ない環境にいる犬は、尿が濃くなりやすく、結石ができるリスクが高くなります。
遺伝的要因
一部の犬種はストルバイト結石ができやすい傾向があります。特にミニチュア・シュナウザー、シーズー、ヨークシャー・テリアなどの犬種は、尿路結石全般にかかりやすいとされています。
このように、ストルバイト結石の原因はさまざまですが、特に尿の性質と生活習慣が深く関わっています。予防のためには、適切な食事管理と水分補給、定期的な排尿を心がけることが重要です。

症状が続く理由と注意すべきポイント
ストルバイト結石の治療を進めているにもかかわらず症状が続く場合、いくつかの原因が考えられます。適切な対処を行わないと、症状が慢性化し、さらなる健康リスクにつながる可能性があるため注意が必要です。
細菌感染が治っていない
ストルバイト結石は細菌性膀胱炎が原因となることが多く、適切な抗菌薬を使用しなければ結石の溶解が進みません。治療を途中でやめてしまったり、効果のない抗菌薬を使用していた場合、感染が残り、結石が再発する可能性があります。
療法食の効果が不十分
ストルバイト結石は、尿のpHを酸性に傾ける療法食によって溶解できます。しかし、適切な食事を与えていない場合や、おやつなどで食事管理が乱れている場合、結石の溶解が進まないことがあります。また、療法食を途中でやめてしまうと、再発することがあるため注意が必要です。
水分摂取が不足している
水分不足は結石の形成を助長します。療法食を適切に与えていても、水を十分に飲まないと尿が濃縮され、新たな結石ができやすくなります。特にドライフード中心の犬は水分摂取量が少なくなりがちなので、ウェットフードを取り入れるなどの工夫が必要です。
排尿回数が少ない
排尿回数が少ないと、膀胱内に結晶が留まりやすくなります。排尿の機会が少ない環境や、おしっこを我慢する癖がある犬では、結石の再発リスクが高まります。
他の結石ができている可能性
ストルバイト結石と同時にシュウ酸カルシウム結石などが存在する場合、ストルバイト結石の治療だけでは改善しないことがあります。シュウ酸カルシウム結石は食事療法で溶解できないため、別の治療が必要になります。
再発しやすい体質
遺伝的に結石ができやすい犬の場合、一度治療しても再発する可能性があります。そのため、治療が終わった後も定期的な尿検査を行い、早期発見・早期対処を心がけることが大切です。
注意すべきポイント
- 定期的な尿検査を受ける → 結石の再発を防ぐために重要
- 療法食の継続が必要か獣医師と相談する → 途中でやめると再発のリスクがある
- おやつや食事管理を徹底する → 療法食以外の食べ物が結石の原因になることも
- 水分補給を促す工夫をする → 常に新鮮な水を用意し、ウェットフードを活用する
- 排尿回数を増やす環境作り → こまめにトイレへ連れて行き、排尿を促す
ストルバイト結石の症状が続く場合、これらのポイントを見直し、適切な対応を取ることが重要です。症状が改善しない場合は、獣医師に相談し、さらなる検査や治療の見直しを行いましょう。
療法食の役割と正しい与え方
ストルバイト結石の治療や予防には、専用の療法食が重要な役割を果たします。しかし、適切な方法で与えなければ効果が十分に発揮されないこともあります。ここでは、療法食の役割と正しい与え方について解説します。
療法食の役割
療法食は、通常のドッグフードとは異なり、ストルバイト結石の形成を防ぐために特別に設計されています。主な役割は以下の通りです。
- 尿を酸性に調整する
ストルバイト結石はアルカリ性の尿で形成されやすいため、療法食には尿のpHを弱酸性に保つ成分が含まれています。 - ミネラル成分を制限する
マグネシウム、リン、カルシウムなどの結石の材料となるミネラルを制限し、新たな結石の形成を防ぎます。 - 水分摂取を促す
一部の療法食にはナトリウム量を調整することで飲水量を増やし、尿を薄める効果があります。これにより、尿中のミネラル濃度を下げ、結晶化を防ぐことができます。
正しい与え方
療法食の効果を最大限に活かすためには、以下のポイントを意識して与えましょう。
- 獣医師の指示に従う
療法食の種類や給与量は、犬の状態によって異なります。必ず獣医師の指示に従い、自己判断でフードを変更しないようにしましょう。 - 療法食のみを与える
おやつや通常のドッグフードを併用すると、療法食の効果が薄れる可能性があります。特に、ミネラル分が多い食材(さつまいもなど)を与えると尿のpHが変化し、結石ができやすくなります。 - 水分補給を意識する
ドライフードのみでは水分が不足しがちです。ウェットフードを取り入れたり、水をこまめに与える工夫をすることで、尿の濃度を下げることができます。 - 定期的に尿検査を行う
療法食が適切に機能しているかどうかを確認するために、定期的な尿検査が推奨されます。獣医師と相談しながら、尿のpHや結晶の有無をチェックしましょう。
療法食は適切に与えることで高い効果を発揮します。しかし、誤った方法で与えると逆効果になることもあるため、食事管理は慎重に行いましょう。

療法食はいつまで続けるべきか?
ストルバイト結石の治療や再発防止には療法食が有効ですが、「いつまで続ければよいのか?」と疑問に思う飼い主も多いでしょう。ここでは、療法食の継続期間について解説します。
治療期間中の療法食の目安
ストルバイト結石が確認された場合、基本的には 結石が溶解するまで療法食を継続 する必要があります。溶解の進行度合いは犬によって異なりますが、多くの場合 1?3か月程度 で結石はなくなります。
ただし、尿検査で結晶がまだ残っている場合は、引き続き療法食を与えることが推奨されます。獣医師の指示に従い、自己判断で通常のフードに戻さないようにしましょう。
予防としての療法食の継続
一度ストルバイト結石を発症した犬は、再発しやすい傾向があります。そのため、結石がなくなった後も予防目的で療法食を続けるケースがあります。
- 再発リスクが高い犬(遺伝的要因、尿のpHが安定しない場合など)は、長期的に療法食を継続 することが推奨されます。
- 水分摂取が少ない犬 や 食事管理が難しい犬 も、療法食の継続が再発防止につながります。
- 定期的な尿検査で異常がないことを確認 しながら、通常のフードに戻せるか判断します。
療法食をやめる際の注意点
療法食をやめる際には、急に通常のフードに戻すのではなく、 徐々に移行 することが大切です。
- 少しずつ通常のフードを混ぜながら切り替える(2週間程度かけて移行すると良い)
- 尿のpHや結晶の有無を定期的に確認する
- 食事を変更した後も水分摂取量を維持する
もし通常のフードに戻した後、頻尿や血尿などの症状が出た場合は、すぐに獣医師に相談 し、再び療法食に戻す必要があるか確認しましょう。
療法食は、ストルバイト結石の治療だけでなく再発防止にも有効です。 「いつまで続けるべきか?」は犬の体質や症状によって異なるため、必ず獣医師と相談しながら適切な判断をすることが大切 です。
おやつの影響は?ストルバイトと食事管理
ストルバイト結石の治療や予防において、おやつの選び方は非常に重要 です。療法食を与えていても、おやつの影響で尿のpHバランスが崩れ、結石が再発する可能性があります。ここでは、ストルバイト結石とおやつの関係、適切な食事管理について解説します。
おやつがストルバイト結石に与える影響
療法食は、尿のpHをコントロールし、結石ができにくい環境を整えるように作られています。しかし、おやつの中には マグネシウムやリン、カルシウムを多く含むものがあり、療法食の効果を打ち消してしまうことがあります。
特に注意が必要なおやつは以下のようなものです。
- チーズやヨーグルト(カルシウムが豊富)
- 魚系のおやつ(リンの含有量が多い)
- 骨付きおやつ(カルシウムが過剰になる可能性がある)
- 塩分の多いおやつ(水分摂取量に影響し、尿の濃度が変わる)
また、おやつの量が増えると、自然と療法食の摂取量が減る ため、療法食の効果が十分に発揮されなくなるリスクもあります。
適切なおやつの選び方
ストルバイト結石の治療中でも、適切な範囲であればおやつを与えることは可能 です。ただし、以下のポイントを守るようにしましょう。
- 低マグネシウム・低リン・低カルシウムのものを選ぶ
- できるだけナトリウム(塩分)が少ないものを選ぶ
- 獣医師が推奨するおやつを使用する
- 与える量を1日のカロリーの10%以内に抑える
市販のおやつを与える場合は、パッケージの成分表を確認し、ミネラルの含有量が少ないものを選ぶことが大切です。また、手作りのおやつを検討する場合は、食材の成分に注意しながら調理しましょう。
おやつを与える際の注意点
おやつを与える際には、食事管理全体を考慮することが重要 です。
- おやつを与えた日は、その分のフード量を調整する
- 水分摂取量を減らさないよう注意する
- おやつの影響で尿のpHが変化しないか、定期的に尿検査を行う
ストルバイト結石の管理には、一貫した食事管理が不可欠です。適切なおやつの選び方と量を守りながら、愛犬の健康をサポートしましょう。
さつまいもは与えても大丈夫?注意点を解説
さつまいもは犬にとって安全な食材のひとつ ですが、ストルバイト結石の管理においては注意が必要です。さつまいもにはシュウ酸が含まれているため、与え方を間違えると尿路結石のリスクが高まる可能性があります。ここでは、ストルバイト結石の犬にさつまいもを与える際の注意点を解説します。
さつまいもがストルバイト結石に与える影響
さつまいもは食物繊維が豊富で消化に良く、ビタミンやミネラルも含まれています。しかし、ストルバイト結石の犬にとっては、いくつかの注意点があります。
- シュウ酸が含まれている
シュウ酸は結石の原因のひとつであり、過剰に摂取すると尿中のカルシウムと結合し、シュウ酸カルシウム結石を形成するリスクが高まります。 - 糖質が多く、肥満の原因になる
さつまいもは炭水化物が多いため、食べ過ぎると肥満につながります。肥満は活動量の低下や水分摂取の減少を引き起こし、ストルバイト結石のリスクを高める可能性があります。 - 尿のpHに影響を与える可能性がある
さつまいも自体はアルカリ性の食品ではありませんが、体質によっては尿のpHバランスに影響を与えることがあります。
さつまいもを与える際の注意点
ストルバイト結石の犬にさつまいもを与える場合は、以下の点に気をつけましょう。
- 少量にとどめる
1回に与える量は 犬の体重の1%以下 を目安にしましょう。 - 加熱して与える
生のさつまいもにはシュウ酸が多く含まれるため、茹でる・蒸す などの方法で加熱することでシュウ酸の量を減らすことができます。 - 皮は取り除く
皮にはシュウ酸が多く含まれるため、皮を剥いてから与えるのが安全 です。 - 頻繁に与えない
週に1?2回程度の頻度で、おやつとして少量を与える 程度にとどめましょう。
さつまいもの代わりにおすすめの食材
もし、ストルバイト結石の犬に与えるおやつとしてさつまいもが不安な場合は、以下の食材を検討すると良いでしょう。
- かぼちゃ(シュウ酸が少なく、ビタミン豊富)
- にんじん(低カロリーで消化に良い)
- りんご(皮をむいて少量ならOK)
ストルバイト結石の管理には、食事のバランスが重要 です。さつまいもは適量であれば問題ありませんが、与え方を誤ると健康に悪影響を及ぼすこともあります。愛犬の体調を見ながら、適切に取り入れるようにしましょう。

犬のストルバイト結石が治らないときの対処法
獣医師に相談すべきタイミングとは?
ストルバイト結石は、早期発見と適切な対応が重要な病気です。症状が軽いうちに治療を始めれば、結石が大きくなるのを防ぎ、手術を回避できる可能性もあります。しかし、適切なタイミングで獣医師に相談しないと、病状が進行し、治療が難しくなることもあります。ここでは、動物病院を受診すべきタイミングについて解説します。
排尿異常が見られたとき
犬が以下のような排尿の異常を示した場合、早めに獣医師の診察を受けましょう。
- 頻繁にトイレに行くが尿の量が少ない
- 排尿時に痛そうな仕草を見せる(鳴く、落ち着きがない)
- 尿に血が混じる(血尿)
- 尿が濁っている、悪臭がある
- 尿が出にくい、またはまったく出ない(これは緊急事態)
特に、尿が出なくなった場合は命に関わるため、すぐに動物病院へ連れて行く必要があります。
療法食や治療を続けても症状が改善しない場合
ストルバイト結石の治療では、療法食や水分摂取の管理が基本となります。しかし、数週間たっても症状が改善しない場合は、適切な治療ができていない可能性があります。
- 療法食を与えているのに結石が溶解しない
- 再発を繰り返している
- 食欲不振や嘔吐などの全身症状が見られる
こうした場合、食事以外の治療法が必要かもしれません。獣医師に相談し、追加の検査や治療を検討しましょう。
再発の兆候があるとき
一度治療が完了しても、ストルバイト結石は再発しやすい病気です。特に、過去に結石を経験した犬は注意が必要です。
- 尿の色が普段と違う(濃い・赤みがある)
- トイレの回数が増えた・減った
- 陰部を頻繁になめる
このような変化が見られたら、再発の兆候かもしれません。早めに診察を受けることで、大きな結石になる前に対処できます。
定期検診を活用する
症状がなくても、定期的に尿検査や超音波検査を受けることが再発防止につながります。特に、ストルバイト結石の既往歴がある犬は、3?6カ月ごとに尿検査を受けると安心です。

ストルバイト結石を防ぐための生活習慣とケア方法
ストルバイト結石は再発しやすい病気のため、日常のケアや生活習慣の見直しがとても重要です。特に、水分摂取、食事管理、運動、排尿管理などをバランスよく行うことで、結石の形成リスクを大幅に減らすことができます。ここでは、具体的な予防策とケア方法について詳しく解説します。
水分摂取を増やし、尿を薄める
ストルバイト結石の予防には、尿を薄めて膀胱内の結晶を流しやすくすることが不可欠です。十分な水分を摂取することで尿量が増え、結石ができにくくなります。
水を飲ませる工夫
- 清潔な水を常に用意する(器は毎日洗い、新鮮な水を維持する)
- 水飲み場を複数設置する(家のあちこちに水を置き、飲む機会を増やす)
- ウェットフードやスープを活用する(水分を含む食事を取り入れる)
- ドライフードをふやかして与える(自然に水分摂取量を増やす)
- 流水式の給水器を導入する(流れる水が好きな犬には効果的)
水分摂取が不足すると尿が濃くなり、結晶が形成されやすくなるため、こまめに水分補給できる環境を整えることが大切です。
食事管理を徹底し、結石のリスクを減らす
ストルバイト結石の再発を防ぐには、食事のミネラルバランスを適切に管理することが重要です。特に、獣医師の指導のもとで療法食を与えることが効果的です。
療法食の活用
- 獣医師と相談して適切な療法食を選ぶ
- 自己判断で一般食に戻さず、定期的に尿検査をしながら調整する
- マグネシウムやリンの摂取量を管理する(これらのミネラルが多いと結石ができやすくなる)
おやつの選び方に注意
食事だけでなく、おやつが結石の原因になることもあるため注意が必要です。
- 避けるべき食材:チーズ、レバー、ほうれん草、ナッツ類(ミネラルが多く結石の原因になる)
- 与えても良いおやつ:さつまいも、かぼちゃ、低リン・低マグネシウムの犬用おやつ
適切な食事管理を徹底し、不要なミネラルを控えることで、結石のリスクを下げることができます。
運動を取り入れ、代謝を向上させる
運動は、水分摂取量の増加、排尿回数の増加、代謝の向上など、ストルバイト結石の予防に多くのメリットがあります。
運動不足が結石に与える影響
- 水を飲む回数が減る → 尿が濃くなり、結晶ができやすくなる
- 排尿回数が減る → 膀胱内で結晶が沈殿しやすくなる
- 肥満になる → 代謝が低下し、結石ができやすくなる
適度な運動を取り入れる方法
- 毎日の散歩を少し長めにする(朝・夕の散歩を15~30分程度)
- 室内でも遊べる運動を取り入れる(ボール遊び、引っ張り合いなど)
- ドッグランなどで自由に走らせる(適度な刺激を与える)
無理なく続けることが大切なので、犬の体調や年齢に合わせて少しずつ運動量を増やしていきましょう。
適切な排尿管理で膀胱内の結晶を排出する
排尿の回数が少ないと、膀胱内に尿が長時間留まり、結晶が沈殿しやすくなります。適切な排尿管理を行い、結晶が尿とともに体外へ排出されるようにすることが重要です。
排尿を促す工夫
- 散歩の回数を増やす(特に朝・晩の排尿を習慣化する)
- トイレの場所を清潔に保つ(不快な環境を避ける)
- 排尿しやすい環境を作る(ストレスのない静かな場所を確保する)
尿の回数が少ないと感じたら、水分摂取量を増やしたり、運動を取り入れることで改善できる場合もあります。
定期的な健康チェックと尿検査を習慣にする
ストルバイト結石は、定期的な健康チェックで早期発見・早期対策を行うことが大切です。特に、過去に結石ができたことがある犬は、定期的な尿検査を行うことで再発を未然に防ぐことができます。
健康管理のポイント
- 半年に1回は尿検査を受ける(結晶の有無やpH値を確認)
- 異常がなくても定期的に病院でチェックを受ける
- 血尿や頻尿などの症状が出たらすぐに獣医師に相談する
獣医師の指導のもと、適切な食事や生活習慣を続けることで、ストルバイト結石のリスクを最小限に抑えることができます。
まとめ:日々のケアでストルバイト結石を防ぐ
ストルバイト結石の予防には、水分摂取、食事管理、適度な運動、排尿管理、定期的な健康チェックの5つのポイントが欠かせません。
- 水をしっかり飲ませ、尿の濃縮を防ぐ
- 療法食を適切に与え、ミネラルバランスを維持する
- 適度な運動を取り入れ、代謝を促進する
- 排尿の回数を増やし、膀胱内に尿をためない
- 定期的な尿検査で早期発見・早期対策を行う
日々のケアを続けることで、ストルバイト結石のリスクを減らし、愛犬が健康で快適に過ごせるようになります。大切なのは、毎日の習慣を見直し、継続することです。愛犬の健康を守るために、できることから始めていきましょう。

犬のストルバイト結石症が治らない原因と正しい対策法について総括
合わせて読みたい!
-

-
【獣医師執筆】犬のストルバイト結晶の原因と食事管理のポイント
犬のストルバイト結晶は、尿の環境がアルカリ性に傾くことで形成されやすくなる病気で、適切な対策を取らなければ再発しやすくなります。ストルバイト結晶の原因には、細菌感染や食事、水分摂取不足などが関係してお ...
続きを見る
-

-
【獣医師執筆】犬の塩分取りすぎによる症状と健康への影響を徹底解説
犬が塩分を取りすぎると、さまざまな健康リスクが発生することをご存知ですか?特に、腎臓や心臓に負担がかかり、命に関わる症状が現れることもあります。「犬 塩分 取りすぎ 症状」で調べている方は、愛犬の健康 ...
続きを見る
-
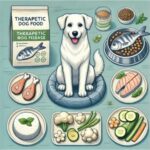
-
【獣医師執筆】犬の腎臓病で絶対に食べさせてはいけないものとは?
愛犬が腎臓病を患ったとき、飼い主として最も気になるのは「どの食材を与えて良いのか」です。犬の腎臓病において食べてはいけないものをしっかりと理解し、適切な食事管理を行うことが、病気の進行を遅らせ ...
続きを見る
