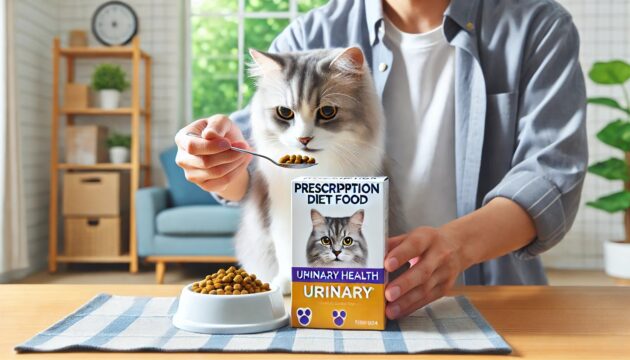
猫のストルバイト結石症の治療期間はどのくらい?症状や薬、療法食の役割、治療中に与えてよいおやつや食べてはいけないものを獣医師が詳しく解説します。ささみはOK?治った後の食生活や再発予防のポイントも紹介。猫のストルバイト結石症の治療期間を短縮するための方法を知りたい方は必見です。愛猫のストルバイト結石症を正しく管理しましょう。
猫 ストルバイト 治療 期間と症状の関係
ストルバイト結石の主な症状とは?

ストルバイト結石は、猫の泌尿器系に影響を及ぼし、排尿に関連するさまざまな症状を引き起こします。初期の段階では軽い違和感のみですが、進行すると深刻な健康リスクを伴うため、早期発見が重要です。
排尿の異常
ストルバイト結石の最も典型的な症状は、排尿時の異常です。具体的には以下のような兆候が見られます。
- 頻尿:短時間で何度もトイレに行くが、少量しか排尿できない
- 排尿困難:トイレで長時間踏ん張るが、尿がなかなか出ない
- 排尿時の痛み:排尿時に鳴く、体を丸めるなどの仕草をする
血尿
結石が膀胱内の粘膜を傷つけることで、血尿が発生することがあります。尿がピンク色や赤みを帯びている場合、出血している可能性が高いです。ただし、血液が微量だと見た目では分かりにくいため、トイレシートや砂に色の変化がないかも確認しましょう。
尿の異臭
通常の尿と比べて強いアンモニア臭がする場合、細菌感染を伴っている可能性があります。特に長期間放置すると膀胱炎を併発し、さらに症状が悪化するリスクがあります。
排尿できない場合は緊急対応が必要
尿道が完全に詰まり、排尿が全くできなくなると、尿毒症を引き起こし命に関わる危険があります。以下のような状態になった場合は、すぐに動物病院を受診してください。
- 何度もトイレに行くが、尿が一滴も出ない
- お腹が膨らんでいる
- 元気がなく、ぐったりしている
このような症状が見られた場合、早急な処置が必要になります。ストルバイト結石は早期に適切な治療を行うことで改善が期待できるため、異変に気付いたらすぐに対応することが大切です。
治療期間の目安と個体差について

ストルバイト結石の治療期間は、猫の状態や治療方法によって異なります。一般的には、食事療法を中心とした場合は2~8週間、外科手術が必要な場合はさらに回復期間を含めて長くなることが多いです。
食事療法による溶解期間
ストルバイト結石は、専用の療法食を用いることで体内で自然に溶かすことができます。この場合、結石が完全に消失するまでの期間は平均2~6週間とされています。
ただし、個体によっては8週間以上かかることもあります。特に以下のような条件では溶解に時間がかかることが多いです。
- 結石のサイズが大きい
- すでに膀胱炎を併発している
- 猫が療法食を十分に食べない
- 水分摂取量が不足している
外科手術が必要な場合
食事療法では対応できないほどの大きな結石や、尿道閉塞を起こしている場合は外科的な摘出手術が必要になります。手術を行った場合、術後の回復期間を含めると完治までに数週間~数カ月かかることがあります。
特に術後は尿路の状態を安定させるために、抗生剤や鎮痛剤の投与、再発予防のための療法食の継続などが必要になります。
個体差による治療期間の違い
同じ治療を行っても、猫によって治療期間には差があります。その要因には以下のようなものがあります。
- 年齢:若い猫は回復が早いが、高齢の猫は治療期間が長くなる傾向がある
- 体質:もともと腎臓や膀胱が弱い猫は治療に時間がかかることがある
- 生活環境:ストレスが多い環境では回復が遅れることがある
- 水分摂取量:水をしっかり飲む猫は尿が薄まり、結石の溶解が早まる
治療期間を短縮するためのポイント
治療をスムーズに進めるためには、飼い主のサポートが重要です。以下のポイントに注意すると、回復が早まる可能性があります。
- 療法食をしっかり食べさせる(他のフードやおやつを与えない)
- 水分摂取を増やす(ウェットフードの活用や水飲み場の増設)
- トイレを清潔に保ち、ストレスを減らす
- 定期的に獣医師の診察を受け、経過をチェックする
ストルバイト結石は、適切な治療を続けることで多くの猫が回復できる病気です。個体差があるため、焦らずに猫の状態を観察しながら、根気よく治療を続けることが大切です。
治療に使われる薬の種類と効果

ストルバイト結石の治療では、薬を使うことで症状の改善や再発防止が期待できます。使用される薬の種類には、大きく分けて抗生物質、尿酸性化剤、鎮痛剤の3つがあります。それぞれの効果を詳しく見ていきましょう。
1. 抗生物質(細菌感染の治療)
ストルバイト結石は細菌感染を伴うことが多いため、適切な抗生物質の投与が必要です。細菌感染があると尿がアルカリ性に傾き、結石が形成されやすくなるため、感染を抑えることで尿のpHバランスを整え、結石の成長を防ぐことができます。主に以下のような抗生物質が使用されます。
- アモキシシリン(広範囲の細菌に有効)
- セファレキシン(尿路感染症に適応)
- エンロフロキサシン(耐性菌にも対応可能)
抗生物質は獣医師の指示のもとで適切に使用することが重要です。自己判断で中断すると、細菌が完全に除去されず、再発リスクが高まります。
2. 尿酸性化剤(尿pHを調整)
ストルバイト結石はアルカリ性の尿で形成されやすいため、尿を酸性に傾けることで溶解を促します。尿酸性化剤は療法食と併用されることが多く、以下の成分が含まれることが一般的です。
- DL-メチオニン(尿pHを低下させる)
- アスコルビン酸(ビタミンC)(酸性化を補助する)
ただし、過度な酸性化はシュウ酸カルシウム結石のリスクを高めるため、定期的な尿検査を行いながら慎重に管理する必要があります。
3. 鎮痛剤(痛みの緩和)
結石が尿路を刺激すると、猫は強い痛みを感じることがあります。痛みがあると排尿を避けるようになり、尿の滞留が進んで症状が悪化する可能性があります。そのため、一時的に鎮痛剤が処方されることがあります。
- メロキシカム(非ステロイド系抗炎症薬)
- ブプレノルフィン(オピオイド系鎮痛剤)
鎮痛剤は根本治療ではなく、あくまで症状を和らげるためのものです。長期間の使用は腎臓への負担となるため、獣医師の指示に従いましょう。
薬の使用に関する注意点
薬を使用する際は、以下の点に注意が必要です。
- 必ず獣医師の指示に従う(自己判断での使用や中止はNG)
- 定期的な尿検査を実施(効果の確認と副作用のチェック)
- 療法食や生活習慣の改善と併用(薬だけに頼らず、総合的な治療を行う)
薬の適切な使用と生活習慣の改善を組み合わせることで、より効果的にストルバイト結石の治療が進められます。
おやつは与えてもよいのか?

ストルバイト結石の治療中や予防を目的とした食事管理では、おやつの扱いに注意が必要です。基本的に、療法食を与えている場合はおやつを避けることが推奨されますが、適切な選び方をすれば、猫の楽しみとして少量を与えることも可能です。
1. おやつが推奨されない理由
ストルバイト結石の管理では、尿のpHバランスやミネラルの摂取量が重要です。しかし、多くの市販のおやつにはマグネシウムやリンが多く含まれており、尿のpHを変化させたり、結石の材料となる成分を摂取してしまう可能性があります。特に以下の理由で注意が必要です。
- 尿のpHが変化する可能性がある(アルカリ性に傾くと結石ができやすくなる)
- マグネシウムやリンを過剰摂取するリスク(結石の成分となる)
- 療法食の効果を妨げる可能性がある(療法食と異なる成分バランス)
そのため、ストルバイト結石の治療中は、おやつの摂取を制限することが基本方針となります。
2. どうしてもおやつを与えたい場合の選び方
猫にとっておやつは楽しみのひとつですが、健康を損なわない範囲で工夫することが大切です。以下のポイントを押さえたおやつなら、少量なら与えても問題が少ないでしょう。
- 低マグネシウム・低リンのものを選ぶ(療法食と同様の成分バランス)
- 無添加・シンプルな素材のものを選ぶ(過剰な栄養素を避ける)
- 与える量はごく少量にする(総カロリーの10%以内が目安)
具体的には、鶏ささみ(茹でただけのもの)や、ストルバイト結石対応のおやつが比較的安全です。ただし、新しいおやつを与える際は、猫の体調を観察しながら慎重に進めましょう。
3. おやつを与える際の注意点
療法食と併用する場合、おやつを与えることが猫の健康に悪影響を与えないように、以下の点に注意してください。
- 獣医師と相談の上で与える(安全性を確認する)
- 与えすぎに注意する(療法食の効果が薄れる)
- 他の食材を混ぜない(特に加工食品や味付きのものは避ける)
ストルバイト結石の再発リスクを減らしながら、おやつを楽しむためには、適切な選び方と適量の管理が重要です。猫の健康を第一に考え、必要であればおやつを控える選択も検討しましょう。
食べてはいけないものリスト

ストルバイト結石の治療中や予防を目的とした食事管理では、特定の食材を避けることが重要です。特に、尿のpHバランスを崩したり、結石の材料となるミネラルを過剰に含む食品は、猫の健康に悪影響を与える可能性があります。以下に、ストルバイト結石の猫に与えてはいけない食べ物をリストアップします。
1. 高マグネシウム・高リンの食材
ストルバイト結石は、リンやマグネシウムが過剰に摂取されると形成されやすくなります。そのため、以下の食材は避けるべきです。
- 煮干し・かつお節(ミネラルが非常に多く含まれる)
- 乳製品(チーズ・ヨーグルト)(リンが多く含まれる)
- 魚の内臓や骨(ミネラルが高濃度で含まれる)
- レバー(鶏・豚・牛)(高リン食材の代表格)
これらの食材は一見健康的に思えますが、ストルバイト結石のリスクを高める可能性があるため、注意が必要です。
2. pHをアルカリ性に傾ける食材
ストルバイト結石は尿がアルカリ性に傾くと形成されやすくなります。そのため、以下の食材は避けるのが賢明です。
- 海藻類(昆布・わかめ・ひじき)(尿をアルカリ性にする)
- 大豆製品(豆腐・納豆)(アルカリ性食材の代表)
- 切り干し大根(アルカリ性が強い)
これらの食材は、健康な猫であれば問題ありませんが、ストルバイト結石の猫には適しません。
3. 塩分や添加物が多い食品
塩分が多いと腎臓に負担がかかり、体内のミネラルバランスが崩れるため、以下の食品も避けるべきです。
- 加工肉(ハム・ベーコン・ソーセージ)
- 味付けされた人間用の食べ物(スープ・煮物・ソース類)
- ペット用でも塩分が多いおやつ(ジャーキー・スナック類)
加工食品には、塩分や化学調味料が多く含まれており、猫の腎臓に負担をかけるため要注意です。
4. 油分や糖分が多い食べ物
脂質や糖分の過剰摂取は、猫の肥満や代謝異常を引き起こし、尿の濃縮を招くため、以下の食品も控えましょう。
- 揚げ物やバターを使った料理
- お菓子(チョコレート・クッキー・ケーキ)
- フルーツ(ぶどう・レーズン・柑橘類)(猫には有害な成分を含むものも)
特に、ぶどうやレーズンは猫の腎機能に悪影響を及ぼすため、絶対に与えてはいけません。
5. ストルバイト結石用療法食との相性が悪い食材
療法食は栄養バランスが綿密に調整されているため、それ以外のフードやトッピングを加えると、効果が弱まる可能性があります。例えば、以下のような組み合わせは避けましょう。
- 通常の総合栄養食との混合(ミネラルバランスが崩れる)
- 自家製ごはんとの併用(pH調整が難しくなる)
ストルバイト結石の猫にとって最適な食事管理を行うためには、療法食を適切に与え、それ以外の食材はできるだけ控えることが大切です。
まとめ
ストルバイト結石の猫が食べてはいけないものは、主に「高ミネラル食材」「pHをアルカリ性にする食材」「塩分・添加物が多い食品」「油分・糖分の多い食品」に分類されます。これらを避けることで、結石のリスクを低減し、健康を維持しやすくなります。
愛猫の健康を守るために、日々の食事管理を意識し、安全なフード選びを心がけましょう。
ささみは与えても問題ない?

猫にとって鶏のささみは消化しやすく、高タンパク・低脂質の優れた食材です。しかし、ストルバイト結石の治療中や予防を目的とする場合には、ささみの与え方に注意が必要です。適切な量と方法を守ることで、安全に活用できます。
1. ささみの栄養とストルバイト結石への影響
ささみはタンパク質が豊富で、脂質が少ないため、猫の健康に良いとされています。ただし、リンの含有量が多く、過剰に摂取すると腎臓への負担が増えたり、尿のミネラルバランスが崩れることがあります。ストルバイト結石の管理においては、尿中のミネラル濃度を適切に保つことが重要なため、ささみの過剰摂取には注意が必要です。
- 高タンパク・低脂質でヘルシー
- リンが多いため、腎臓に負担をかける可能性がある
- ミネラルバランスが崩れると、結石ができやすくなる
2. ささみを与える際のポイント
ストルバイト結石の猫にささみを与える場合は、以下の点に注意しましょう。
- 量を制限する:療法食と併用する場合は、おやつ程度にとどめる(1日の総カロリーの10%以下が目安)。
- 調理方法に気をつける:必ず茹でて、味付けをせずに与える。塩や調味料は猫にとって有害な可能性がある。
- リンの摂取量を考慮する:リンの多い食材を控え、総合的な栄養バランスを獣医師と相談しながら調整する。
- ささみのゆで汁は活用できる:水分補給のために、ささみのゆで汁を薄めて与えるのも有効。ただし、余分な脂肪や成分が含まれていないか確認する。
3. ささみは療法食の代わりにはならない
ささみは栄養価が高いものの、療法食とは異なり、ストルバイト結石の管理に必要なミネラルバランスや尿pHの調整機能を持っていません。あくまで補助的な食品として利用し、主食は獣医師が推奨する療法食を継続することが大切です。
療法食の効果を損なわないよう、ささみを与える場合は適量を守り、猫の健康状態を確認しながら進めるようにしましょう。
猫 ストルバイト 治療 期間を短縮するためにできること
獣医師の診察を受けるタイミング

ストルバイト結石の管理には、適切なタイミングでの獣医師の診察が欠かせません。早期に異常を発見し、適切な治療を受けることで、症状の悪化を防ぐことができます。
1. 排尿に関する異変が見られたとき
排尿トラブルは結石のサインであることが多く、以下のような症状が見られた場合は早めに診察を受けましょう。
- トイレの回数が増えた(頻繁にトイレに行くが、少量しか出ない)
- 排尿時に鳴く(痛みを感じている可能性がある)
- トイレ以外の場所で粗相をする(膀胱炎の影響も考えられる)
- 尿が濁っている、血尿が出る(結晶や炎症の可能性がある)
特にオス猫は尿道が細く、詰まりやすいため、完全に排尿ができなくなる「尿道閉塞」のリスクがあります。24時間以上尿が出ない場合は緊急性が高いため、すぐに病院へ連れて行きましょう。
2. 体調に変化が見られたとき
ストルバイト結石は尿の異常だけでなく、猫の全身状態にも影響を与えることがあります。
- 食欲が落ちた(痛みや不快感から食事を拒むことがある)
- 元気がなくなった(動かずにじっとしている時間が増える)
- 嘔吐する(尿毒症の初期症状の可能性も)
これらの症状が長引く場合は、結石の悪化や膀胱炎の進行が考えられるため、すぐに診察を受けるべきです。
3. 療法食の効果が見られないとき
ストルバイト結石の治療では、適切な療法食を与えることで結石を溶かすことが可能ですが、以下のような場合は獣医師に相談する必要があります。
- 1か月以上経過しても改善が見られない(フードの変更が必要な可能性がある)
- 療法食を食べない(他の選択肢を検討する必要がある)
- 結石が大きくなっている(手術が必要になるケースもある)
結石の状態に応じて、フードの種類を変えたり、追加の治療を検討することが重要です。
4. 定期検診のタイミング
一度結石を経験した猫は、治療後も定期的な健康診断を受けることが推奨されます。
- 尿検査(pHや結晶の有無をチェックする)
- 超音波検査(膀胱内の状態を確認する)
- 血液検査(腎臓の健康状態を把握する)
特に治療後6か月以内は、再発のリスクが高いため、定期的に尿検査を受けると安心です。
5. 再発の兆候が見られたとき
過去にストルバイト結石を経験した猫が、再び以下のような症状を示した場合、すぐに診察を受けることをおすすめします。
- トイレの回数が増えた、または減った
- 尿の色が変わった(赤みがかっている、白く濁っている)
- 水を飲む量が極端に減った、または増えた
再発を防ぐためには、早期発見が重要です。少しでも異変を感じたら、獣医師に相談し、適切な対応をとりましょう。
猫の健康を守るためには、定期的な診察と早めの対応が不可欠です。普段から愛猫の様子を観察し、異変を見逃さないよう心がけましょう。
ストルバイト結石の療法食と水分管理の重要性

ストルバイト結石の治療や再発防止には、適切な療法食の選択と水分摂取の工夫が欠かせません。猫は本来、水を積極的に飲まない動物のため、フードと組み合わせて水分を補給できる環境を整えることが必要です。ここでは、療法食の重要性と選び方、水分摂取を促す工夫について詳しく解説します。
1. 療法食が必要な理由
ストルバイト結石は、尿中のリンやマグネシウムが過剰になり、尿のpHがアルカリ性に傾くことで形成されます。療法食はこれらのミネラルバランスを調整し、尿のpHを適切な範囲(6.0前後)に保つことで、結石の溶解や再発防止をサポートします。
療法食の主な特徴
- 低マグネシウム・低リン:結石の形成を防ぐため、ミネラル含有量を制限。
- 尿の酸性化:DL-メチオニンやクランベリー抽出物を含み、尿pHをコントロール。
- 水分量の確保:ウェットフードなら約80%の水分を含み、尿の濃縮を防ぐ。
- 尿量の増加:ナトリウムの調整により尿の排出を促進し、結晶の蓄積を防ぐ。
2. 療法食の選び方
療法食にはさまざまな種類があり、猫の体質や好みに合わせて選ぶことが大切です。以下のポイントを参考にしましょう。
(1) 獣医師の推奨するフードを選ぶ
療法食は医薬品ではないものの、治療の一環として重要な役割を持つため、獣医師と相談のうえ適切なフードを選ぶことが必要です。
代表的なストルバイト結石向け療法食
- ロイヤルカナン ユリナリーS/O:ストルバイトの溶解と再発予防に優れる。
- ヒルズ c/d マルチケア:長期使用に適したバランスの良い療法食。
- ベッツワン pHケア:コストを抑えつつ尿pHを調整できる。
(2) ウェットフードを優先する
猫は水をあまり飲まないため、水分摂取量を増やす目的で、可能な限りウェットフードを選ぶのが理想です。ドライフードを与える場合でも、水分を補う工夫を取り入れましょう。
(3) 猫の食いつきを考慮する
療法食は一般のフードと風味が異なるため、猫が食べてくれない場合もあります。その際は以下の工夫を試しましょう。
- 少量ずつ混ぜて慣れさせる
- フードを温めて香りを強くする
- ウェットフードに切り替える
療法食を拒否したからといって、通常食に戻すと治療が進まず、結石のリスクが高まります。猫が慣れるまで根気よく調整しましょう。
3. 水分摂取を促す工夫
水分摂取量が少ないと尿が濃縮され、結晶ができやすくなります。以下の方法で、猫が自然に水を飲む習慣をつけられるよう工夫しましょう。
(1) 水分補給のための具体的な方法
- ウェットフードを積極的に活用する:水分含有量が80%以上あるため、自然に水分を摂取できる。
- 水飲み場を増やす:家の数カ所に水皿を置くことで、飲む機会を増やせる。
- 流れる水を利用する:自動給水器を使うと、新鮮な水に興味を持ちやすくなる。
- 水分補給に適したフードを利用する:スープタイプの療法食や、ささみのゆで汁を薄めて与えるのも効果的。
- ドライフードに水を加える:少量の水でふやかし、半湿状態で与えると水分摂取量が増える。
(2) 食事と水分補給を組み合わせる工夫
- ドライとウェットを併用する:完全にドライフードをやめるのが難しい場合は、ウェットフードを組み合わせて与える。
- 食事の回数を増やす:1回の食事量を減らし、回数を増やすことで、1日を通して水分摂取を促す。
- フレーバーウォーターの活用:無添加のスープや薄めたささみのゆで汁を活用する。
4. 療法食と水分管理を継続する重要性
ストルバイト結石の治療は、一度完了したからといって終わりではありません。再発リスクを抑えるためには、食事と水分管理を継続することが不可欠です。
(1) 療法食の使用期間と注意点
療法食の使用期間は猫の状態によって異なりますが、以下の点に注意しながら適切に管理しましょう。
- 療法食を他のフードと混ぜない:効果が薄れる可能性があるため、単独で与えるのが基本。
- 間食やおやつを控える:療法食のバランスが崩れると、尿pHが変化し、再発リスクが高まる。
- ストルバイトが溶解した後の管理を考える:通常食に戻す場合は、獣医師と相談しながら慎重に進める。
(2) 水分摂取の継続的な管理
- 猫の水分摂取量を定期的にチェックし、十分な水分を摂れているか確認する。
- 尿の状態を観察し、色や濁りがあれば早めに受診する。
- 定期的な尿検査を受けることで、再発リスクを低減できる。
5. まとめ:食事と水分管理のバランスを意識しよう
ストルバイト結石の治療と予防には、療法食と水分管理をバランスよく組み合わせることが大切です。以下のポイントを意識しながら、継続的にケアを行いましょう。
療法食は獣医師と相談しながら選ぶ
可能な限りウェットフードを取り入れ、水分摂取量を増やす
水飲み場の増設や自動給水器を活用し、飲水量を確保する
食事回数を調整しながら、水分補給を促す
定期的な尿検査を行い、異常がないか確認する
これらの対策を実践することで、ストルバイト結石の再発リスクを抑え、猫が健康に過ごせる環境を整えることができます。愛猫の健康維持のために、日々の食事と水分管理を工夫していきましょう。
ストルバイト結石が治った後の食生活と再発予防のポイント

ストルバイト結石が治った後も、再発のリスクを減らすためには、適切な食生活と生活習慣の管理が必要です。結石は一度溶解しても、食事や水分摂取が不適切だと再発しやすいため、油断せずに継続的なケアを行いましょう。ここでは、治療後の食事管理と再発を防ぐための具体的な方法を紹介します。
1. 療法食の継続か通常食への移行かを判断する
ストルバイト結石が治った後、療法食を続けるべきか、通常のフードに戻すべきかは、猫の体質や獣医師の指導によります。以下の選択肢を検討しましょう。
① 療法食を継続する場合
- 再発リスクが高い猫(過去に何度も結石ができた経験がある場合)は、予防のために療法食を継続する方が安心。
- 膀胱炎を繰り返しやすい猫も、尿のpHバランスを維持する療法食を与えたほうが良い。
- 総合栄養食として使える療法食(例:ストルバイト予防用フード)を選び、長期的に与えるのも一つの方法。
② 通常の総合栄養食に戻す場合
- 一度結石が溶解し、尿検査で異常がない場合、通常食に戻しても問題ないことがある。
- pHバランスが適正なフード(尿の酸性度を適切に保つもの)を選び、再発しないよう注意する。
- 療法食→通常食への切り替えは慎重に行い、段階的に移行する。
③ 総合栄養食+サプリメントを併用する
- クランベリーエキスやメチオニンなど、尿pHを調整する成分を含むサプリメントを活用するのも選択肢の一つ。
- 獣医師と相談しながら、食事とサプリメントのバランスを考える。
2. 水分摂取量を維持し、尿の濃縮を防ぐ
水分不足は、尿を濃縮させ、結晶が形成される原因になります。治療後も水分摂取量を意識して維持しましょう。
水分摂取を増やす方法
- ウェットフードを積極的に取り入れる:ドライフードのみでは水分量が不足しがち。ウェットフードは水分含有量が80%以上と豊富なので、積極的に与えると良い。
- 新鮮な水を常に用意する:猫はきれいな水を好むため、こまめに交換し、飲みやすい環境を整える。
- 水飲み場を複数設置する:家の中に数か所、水を飲める場所を作ることで、水を飲む機会を増やせる。
- 自動給水器を活用する:流れる水を好む猫には、自動給水器が有効。
- フードに水を加える:ドライフードをふやかしたり、ささみのゆで汁を薄めて加えると、自然に水分を摂取できる。
3. 定期的な尿検査で早期発見・早期対応を
ストルバイト結石は再発しやすいため、定期的な尿検査を受けることで、再発の兆候を早期に発見できます。
尿検査でチェックすべきポイント
- 尿pHの確認:ストルバイト結石はアルカリ性尿で形成されるため、pH6.0~6.5の範囲を維持するのが理想。
- 尿中の結晶の有無:小さな結晶が見つかれば、結石の形成が始まっている可能性がある。
- 尿の色や臭い:尿の濁りや血尿がある場合、膀胱炎の兆候があるため注意が必要。
尿検査の頻度
- 治療後3か月以内:1か月ごとに尿検査を受けるのが理想的。
- 症状が安定した後:半年~1年に1回の定期検診で状態をチェックする。
4. ストレスを軽減し、膀胱の健康を守る
ストレスは膀胱炎の発症リスクを高め、それがストルバイト結石の再発につながることがあります。猫が快適に過ごせる環境を整え、ストレスを最小限に抑えることが重要です。
ストレスを軽減するための工夫
- トイレ環境の改善:トイレは常に清潔に保ち、猫の好みに合った砂を使用する。トイレの数は「猫の頭数+1」が理想。
- 静かで落ち着ける空間を確保する:騒がしい環境を避け、猫が安心できるスペースを作る。
- 多頭飼いなら個別の居場所を用意する:猫同士の相性が悪い場合、別々の空間で過ごせるようにする。
- 遊びの時間を確保する:ストレス解消と運動不足の解消を兼ねて、1日数回遊ぶ時間を作る。
5. 適度な運動を取り入れ、健康維持を図る
運動は、ストレス軽減だけでなく、尿の排出を促す効果も期待できます。猫が適度に運動できる環境を整えましょう。
運動不足を防ぐ方法
- キャットタワーやおもちゃを活用する:猫が自然に動けるよう、運動量を増やせるアイテムを設置する。
- インタラクティブなおもちゃを使う:猫じゃらしや自動で動くおもちゃを利用して、楽しく運動させる。
- 飼い主と一緒に遊ぶ:定期的に遊びの時間を作り、猫の運動を促す。
6. まとめ:治療後も継続的な管理が必要
ストルバイト結石は一度治っても、再発しやすい病気です。そのため、適切な食事管理と水分補給、ストレス対策を継続することが大切です。
治療後に意識すべきポイント
食の継続か通常食への移行を慎重に判断する
水分摂取を意識し、尿を薄める習慣を継続する
定期的な尿検査を受け、異常がないかチェックする
ストレスを軽減し、膀胱の健康を守る環境を整える
適度な運動を取り入れ、健康維持を図る
このような管理を続けることで、ストルバイト結石の再発リスクを減らし、愛猫が健康で快適な生活を送れるようサポートしましょう。
猫ストルバイト結石症の治療期間と療法食の重要性について総括
合わせて読みたい!
-

-
【獣医師執筆】心臓病の猫に気をつけることと食事管理のポイント
猫の心臓病は、初期症状がわかりにくいため、気づかないまま進行してしまうことがあります。しかし、早期発見と適切な管理を行うことで、猫の生活の質を維持することが可能です。この記事では、心臓病の猫において気 ...
続きを見る
