
猫のストルバイト結石症は、泌尿器系のトラブルの中でも特に注意が必要な病気の一つで、放置すると猫の寿命に影響を与える可能性があります。初期症状を見逃さず、早期に適切な対処を行うことで、改善や完治が期待できる病気でもあります。ストルバイト結石にはいくつかの種類があり、治療には療法食の活用が重要です。本記事では、ストルバイト結石症の症状や治療法、猫の寿命を延ばすための管理方法について、獣医師が詳しく解説します。
猫のストルバイト結石症 寿命と病気の関係
ストルバイト結石の主な症状とは?
ストルバイト結石は、猫の泌尿器に影響を与え、排尿に関する異常が現れることが特徴です。初期の段階では軽い違和感しか感じられないこともありますが、進行すると深刻な健康リスクにつながるため、早期発見が重要です。
1. 排尿時の異常
ストルバイト結石ができると、尿の通りが悪くなり、以下のような症状が現れることがあります。
- 頻尿:トイレに何度も行くが、一度に出る尿の量が少ない
- 排尿困難:トイレで長く踏ん張るが、尿がなかなか出ない
- 排尿時の痛み:尿を出すときに鳴く、体を丸めるなどの仕草をする
これらの異常が見られた場合、早めに動物病院を受診することが望ましいです。
2. 血尿や尿の異臭
結石が膀胱内の粘膜を傷つけることで、血尿が出ることがあります。尿がピンク色や赤みを帯びている場合、出血している可能性が高いです。また、細菌感染を伴う場合は尿の臭いが強くなることもあります。
3. トイレ以外での排尿(粗相)
排尿時に痛みを感じると、猫はトイレを嫌がるようになることがあります。その結果、カーペットや布団の上など、やわらかい場所で排尿してしまうことがあります。
4. 尿が出なくなる(緊急対応が必要)
尿道が完全に詰まると、尿が出せなくなり、短時間で命に関わる状態に陥ることがあります。以下のような状態になったら、すぐに動物病院へ行く必要があります。
- 何度もトイレに行くが、一滴も尿が出ない
- お腹が張っている、触ると嫌がる
- ぐったりして動かなくなる
ストルバイト結石は、適切な対処をすれば治療が可能な病気です。症状に気づいたら、早めに診察を受けることが大切です。

ストルバイト結石の原因と影響
ストルバイト結石は、尿の中にミネラル成分が結晶化してできるものです。結石が形成される原因はいくつかあり、環境や食生活の影響を大きく受けることが知られています。
1. 水分不足
猫は本来、水をあまり飲まない動物です。水分摂取量が少ないと尿が濃縮され、ストルバイト結石の原因となるミネラル成分が結晶化しやすくなります。特に、ドライフードのみの食生活を続けている猫は、尿の濃度が高まりやすいため注意が必要です。
2. 食事の影響
ストルバイト結石は、尿がアルカリ性に傾いたときにできやすくなります。マグネシウムやリンを多く含む食事を続けると、尿のpHが変化し、結石のリスクが高まります。
3. 運動不足と肥満
運動不足になると、新陳代謝が低下し、尿の流れが悪くなります。尿が膀胱に長くとどまると、結石が形成されるリスクが上がります。また、肥満の猫は活動量が少なく、トイレの回数も減りがちです。
4. ストレスや生活環境
猫は環境の変化に敏感な動物です。引っ越しや新しいペットの導入、トイレの場所の変更などのストレスがかかると、排尿の回数が減り、尿が濃縮される原因になります。
5. ストルバイト結石がもたらす影響
ストルバイト結石ができると、膀胱や尿道にダメージを与え、以下のような影響を及ぼします。
- 膀胱炎の併発:結石が膀胱内を傷つけることで、細菌感染を引き起こすことがある
- 尿道閉塞:尿道が詰まると尿が出せなくなり、緊急手術が必要になることもある
- 慢性腎臓病のリスク:長期間にわたって膀胱や腎臓に負担がかかると、腎機能が低下する可能性がある
6. ストルバイト結石の予防と対策
ストルバイト結石を防ぐためには、以下の対策が有効です。
- 水分をしっかり摂らせる:ウェットフードの活用や水飲み場の増設を行う
- バランスの取れた食事を与える:療法食やpHコントロールフードを活用する
- 運動量を確保する:適度な運動を取り入れ、代謝を促進する
- ストレスを減らす:生活環境を整え、安心できる空間を作る
ストルバイト結石は、一度できると再発しやすい病気です。生活習慣を見直し、日頃から予防を意識することで、猫の健康を守ることができます。
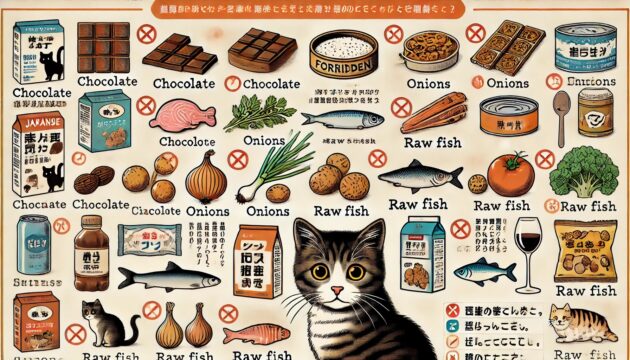
早期発見と治療期間が猫の寿命に与える影響
ストルバイト結石は、猫の泌尿器に影響を及ぼし、放置すると深刻な健康リスクにつながる病気です。しかし、早期発見と適切な治療を行うことで、寿命への悪影響を最小限に抑えることができます。ここでは、早期発見の重要性と治療期間が寿命に与える影響について解説します。
1. 早期発見が寿命を延ばす理由
ストルバイト結石は、初期の段階で適切な対応をすれば、比較的短期間で改善が期待できる病気です。しかし、発見が遅れると症状が悪化し、以下のような深刻なリスクを伴います。
- 膀胱炎や尿道閉塞の発症(尿が排出されず、緊急対応が必要になる)
- 腎臓への負担増加(尿の流れが滞ることで腎機能が低下する)
- 尿毒症のリスク(体内の老廃物が排出されず、命に関わる状態になる)
特に尿道閉塞は、発症から数日以内に適切な治療をしなければ命に関わるため、早期発見が極めて重要です。
2. 治療期間と猫の健康への影響
ストルバイト結石の治療期間は、猫の体質や病状によって異なりますが、以下のような目安があります。
- 療法食による治療:2?8週間で結石が溶解することが多い
- 抗生物質の使用:膀胱炎を併発している場合、1?2週間の服用が必要
- 外科手術の場合:手術後の回復期間を含め、数週間?数カ月
治療が遅れるほど合併症のリスクが高まり、結果として寿命を縮める可能性があるため、早期対応が不可欠です。
3. 早期発見のために飼い主ができること
猫の健康を守るためには、日常的に異変に気づくことが大切です。以下のポイントを意識して観察しましょう。
- トイレの回数や時間をチェックする(頻繁に行く、長時間踏ん張るなど)
- 尿の色や臭いを確認する(血尿や強いアンモニア臭がないか)
- 食欲や元気の変化を見逃さない(食欲不振や活動量の低下がないか)
また、定期的に尿検査を受けることで、症状が出る前に異常を発見できる可能性が高まります。
4. 早期治療が寿命を延ばすためのポイント
ストルバイト結石は、適切な食事管理と水分摂取の工夫で予防できる病気です。早期治療を進めるために、以下の点を意識しましょう。
- 療法食を適切に与える(自己判断で通常食に戻さない)
- 水分摂取を増やす(ウェットフードや自動給水器を活用する)
- 定期的に尿検査を受ける(早期発見のための健康管理)
早めの対策と継続的なケアを行うことで、ストルバイト結石による猫の寿命への影響を最小限に抑えることができます。飼い主がしっかりと管理し、愛猫の健康を守ることが何よりも大切です。
ストルバイト結石は治るのか?
ストルバイト結石は適切な治療を行えば、多くの場合で改善が可能な病気です。しかし、治療方法や猫の体質によっては時間がかかることもあり、再発を防ぐための継続的なケアが必要になります。
1. ストルバイト結石は溶解できる
ストルバイト結石は、療法食や水分摂取を適切に管理することで、尿のpHを調整しながら溶かすことが可能です。一般的に、専用の療法食を与え始めると2~8週間程度で結石が消失することが多いとされています。
2. 外科手術が必要な場合もある
結石が大きすぎたり、尿道閉塞を引き起こしている場合は、食事療法だけでは対処できず、外科手術が必要になることもあります。特に、尿道が詰まってしまうと命に関わるため、迅速な処置が求められます。
3. 一度治っても再発しやすい
ストルバイト結石は、治療後も再発しやすい病気の一つです。そのため、以下のような予防策を継続的に実施することが大切です。
- 療法食やpHコントロールフードを活用する
- 水分摂取量を増やし、尿を薄める
- 定期的な尿検査を受け、早期発見に努める
4. 完全に治るかは生活習慣次第
ストルバイト結石は一度治療すれば終わりというわけではなく、日々の生活管理が重要になります。適切な食事や水分管理を続けることで、再発リスクを最小限に抑えることができます。
ストルバイト結石は適切な対応をすれば改善できる病気ですが、再発しないように継続的なケアが必要です。猫の健康を守るために、食事や生活環境の管理を意識し、定期的な健康チェックを行いましょう。

猫の種類によって寿命は異なる?
猫の寿命は、品種によってある程度の違いがあります。純血種と雑種、体の大きさや遺伝的要因などが関係し、それぞれの猫が持つ健康リスクも異なるためです。しかし、生活環境や食事、医療の質によっても大きく左右されるため、一概に「この品種は長生きしやすい」とは言い切れません。
1. 純血種と雑種の寿命の違い
一般的に、雑種の猫の方が純血種よりも長生きするとされています。その理由として、遺伝的な疾患を持ちにくいことが挙げられます。
- 雑種の猫:遺伝的多様性が高く、特定の病気にかかりにくい傾向がある
- 純血種の猫:品種特有の遺伝疾患を持つ場合があり、健康管理がより重要
例えば、ペルシャ猫は腎臓病にかかりやすく、メインクーンは心臓病のリスクが高いなど、それぞれの品種に特有の健康リスクがあります。そのため、純血種の猫を飼う場合は、遺伝的な疾患に注意しながら適切なケアを行うことが必要です。
2. 体の大きさと寿命の関係
猫のサイズも寿命に影響を与える要素の一つです。
- 小型~中型の猫:平均15年前後の寿命を持つことが多い
- 大型の猫(メインクーンなど):平均10?13年とやや短め
一般的に、大型の猫ほど寿命が短くなる傾向があります。これは心臓や関節への負担が大きくなるためと考えられています。
3. ストルバイト結石のリスクと猫の種類
ストルバイト結石は、特定の猫種だけでなく、すべての猫に発生する可能性がある病気です。しかし、一部の猫種では尿路系の病気にかかりやすい傾向が見られます。
- ペルシャ、ヒマラヤン、エキゾチックショートヘア:尿路系のトラブルが多く、ストルバイト結石のリスクも高め
- シャム、バーミーズ:細身の体型のため、腎臓や膀胱に関わる病気の管理が必要
どの品種であっても、適切な食事と水分管理を行うことで、ストルバイト結石のリスクを減らし、健康的な生活を維持することができます。
4. 品種だけでなく生活環境も寿命に影響
猫の寿命は品種だけで決まるわけではなく、日々の生活環境も大きく関係します。
- 室内飼育の猫:感染症や事故のリスクが少なく、平均寿命が長くなる
- 外飼いの猫:交通事故や感染症のリスクが高く、寿命が短くなる傾向
また、定期的な健康診断を受けることで、病気の早期発見が可能になり、寿命を延ばすことにつながります。品種ごとの違いを理解しつつ、生活環境を整えることが猫の健康を守るポイントになります。
猫のストルバイト結石症 寿命を延ばすためにできること
療法食の役割と選び方
ストルバイト結石の治療や予防には、適切な療法食を与えることが重要です。療法食は、一般的なフードとは異なり、尿のpHを調整し、結石の形成を防ぐために特別に設計されています。ここでは、療法食の役割と選び方について解説します。
1. 療法食の役割
ストルバイト結石の療法食には、主に以下のような機能があります。
- 尿のpHを適正範囲に調整する(酸性に保つことで結石の形成を抑制)
- ミネラルバランスを調整する(マグネシウムやリンの量を制限し、結石の成分を減らす)
- 尿量を増やし、結晶の排出を促す(ナトリウム調整により尿の排泄を促進)
適切な療法食を与えることで、結石の溶解や再発予防が期待できます。
2. 療法食の選び方
猫の体質や好みに合った療法食を選ぶことが、治療の成功につながります。選ぶ際のポイントは以下の通りです。
(1) 獣医師の推奨を優先する
療法食にはさまざまな種類があり、猫の状態に合わせたフードを選ぶことが重要です。特に以下のような療法食が推奨されることが多いです。
- ロイヤルカナン ユリナリーS/O(ストルバイトの溶解と再発予防に特化)
- ヒルズ c/d マルチケア(長期管理向けで、膀胱炎予防にも適している)
- ベッツワン pHケア(コストを抑えつつ尿pHを調整可能)
(2) ウェットフードを優先する
ドライフードに比べてウェットフードの方が水分含有量が高いため、尿を薄める効果があります。可能であれば、ウェットタイプの療法食を選ぶと良いでしょう。
(3) 猫の好みに合ったものを選ぶ
療法食は通常のフードとは味や香りが異なるため、猫が食べない場合もあります。その際は以下の方法で工夫してみましょう。
- 少しずつ混ぜながら切り替える
- フードを軽く温めて香りを引き立てる
- ドライフードに水を加え、半湿状態にする
3. 療法食の注意点
療法食を与える際には、以下の点に注意しましょう。
- 他のフードやおやつと併用しない(栄養バランスが崩れ、効果が弱まる)
- 適量を守る(食べ過ぎは体重増加や消化不良の原因となる)
- 定期的に尿検査を行い、効果を確認する
4. 療法食の使用期間と継続管理
ストルバイト結石が溶解した後も、療法食を続けるべきかどうかは猫の状態によります。
- 再発リスクが高い場合:療法食を継続することが推奨される
- 健康状態が安定した場合:総合栄養食へ移行できる可能性がある
療法食の変更は、必ず獣医師と相談しながら慎重に進めることが大切です。
適切な療法食を選び、正しく管理することで、ストルバイト結石のリスクを抑え、猫の健康を守ることができます。

水分摂取が寿命に与える影響
猫の健康維持には十分な水分摂取が欠かせません。特に泌尿器系の病気を予防するためには、適切な水分補給が重要です。水をしっかり飲める環境を整えることで、病気のリスクを減らし、猫の寿命を延ばすことが期待できます。
1. 水分不足が健康に及ぼすリスク
猫はもともと砂漠地帯に生息していた動物であり、水を積極的に飲む習慣が少ないといわれています。そのため、慢性的な水分不足に陥りやすく、以下のような健康リスクが高まります。
- 尿路結石や膀胱炎のリスク増加(尿が濃縮され、結晶や細菌が増えやすくなる)
- 腎臓病の発症リスク上昇(老廃物の排出が不十分になり、腎臓への負担が増える)
- 便秘の原因となる(腸内の水分が不足し、硬い便が形成される)
特にストルバイト結石の予防には、十分な水分摂取が不可欠です。
2. 適切な水分摂取が寿命を延ばす理由
十分な水を摂取することで、腎臓や膀胱にかかる負担が軽減され、病気の発症を防ぐことができます。これにより、慢性的な疾患のリスクが下がり、結果として猫の寿命を延ばすことにつながります。
- 尿が適度に希釈され、結石の形成を防ぐ
- 老廃物がスムーズに排出され、腎機能を保護する
- 腸内環境が整い、消化器系の健康も維持される
適切な水分摂取は、病気を未然に防ぐだけでなく、猫の体全体の健康を支える重要な要素です。
3. 水分摂取を増やすための工夫
猫が自然に水を飲む量を増やせるよう、飼い主が環境を整えることが大切です。以下のような工夫を取り入れると、飲水量を増やせる可能性があります。
- ウェットフードを取り入れる(水分含有量が高く、食事とともに水分補給ができる)
- 複数の水飲み場を用意する(猫が気軽に水を飲めるようにする)
- 自動給水器を活用する(流れる水を好む猫には特に効果的)
- 水の味や温度を変えてみる(猫によってはぬるま湯や湧き水を好む場合もある)
猫が無理なく水を飲める環境を整えることで、健康維持に役立てることができます。
適切な水分摂取は猫の寿命を延ばす大きな要素です。日々の飲水量を意識し、健康的な生活をサポートしていきましょう。
ストルバイト結石の予防と再発防止のための管理方法
ストルバイト結石は適切な管理を続けることで予防や再発防止が可能です。食事の見直しや水分摂取の工夫、生活環境の改善を組み合わせることで、結石の形成リスクを減らし、猫の健康を維持できます。ここでは、ストルバイト結石を防ぐための日常的なケアについて詳しく解説します。
1. 水分摂取を増やして尿を薄める
ストルバイト結石は、尿が濃縮されることで形成されやすくなります。そのため、猫が十分な水分を摂取できる環境を整えることが重要です。
効果的な水分摂取の工夫
- ウェットフードを活用する(水分含有量が高く、自然に水分を補給できる)
- 複数の水飲み場を用意する(猫がいつでも水を飲めるようにする)
- 自動給水器を使用する(流れる水を好む猫が多いため、飲水量が増える可能性がある)
- ささみの茹で汁や無添加スープで風味をつける(水を好まない猫の飲水量を増やす工夫)
- 食事の回数を増やす(食後に水を飲む習性を活用して水分摂取を促す)
2. 適切な食事管理を行う
食事はストルバイト結石の予防・管理に最も影響を与える要素の一つです。適切なフードを選び、尿のpHを適切にコントロールしましょう。
食事管理のポイント
- 療法食やpHコントロールフードを活用する(尿の酸性化を助ける成分を含む)
- マグネシウムやリンの過剰摂取を避ける(結石の形成を防ぐ)
- おやつや加工食品を控える(高ミネラルな食材が結石の原因になる)
- 総合栄養食を基本とし、偏りのない栄養バランスを意識する
特に、一度ストルバイト結石を経験した猫は、通常食への切り替えを慎重に行い、獣医師と相談しながら管理することが大切です。
3. 定期的な尿検査を受ける
ストルバイト結石は、初期段階で発見できれば療法食や水分管理で改善できることが多いため、定期的に尿検査を受けることが推奨されます。
検査の重要ポイント
- 尿のpH値をチェックする(6.0?6.5の範囲が理想)
- 結晶の有無を確認する(目に見えない段階での発見が可能)
- 膀胱炎や細菌感染の有無を調べる(結石形成の原因を特定する)
- 症状がなくても半年?1年に1回は尿検査を受ける
4. 快適なトイレ環境を整える
猫はトイレ環境が悪いと排尿を我慢することがあり、尿の濃縮を招いて結石のリスクを高めてしまいます。
理想的なトイレ環境のポイント
- トイレの数は「猫の頭数+1」が理想(複数の選択肢を用意する)
- トイレを常に清潔に保つ(排尿を我慢すると膀胱炎や尿石症の原因になる)
- 猫の好みに合った砂を使用する(トイレ嫌いを防ぐ)
- 排尿の頻度や尿の状態をこまめに観察する(異常の早期発見につながる)
5. ストレスの少ない生活環境を作る
ストレスは猫の泌尿器系に悪影響を及ぼし、膀胱炎や結石の原因になることがあります。猫がリラックスして過ごせる環境を整えましょう。
ストレス軽減のための工夫
- 静かで落ち着けるスペースを用意する(騒音や頻繁な環境の変化を避ける)
- 多頭飼いの場合は個別の居場所を確保する(相性によるストレスを軽減)
- 適度に遊ぶ時間を確保する(運動不足やストレスが結石形成につながる)
- フェリウェイなどのリラックス効果のあるアイテムを活用する(環境の変化によるストレスを緩和)
6. 規則正しい生活を心がける
生活習慣が乱れると、体内のホルモンバランスや代謝が影響を受け、泌尿器系の健康に悪影響を及ぼすことがあります。
健康的な生活習慣のポイント
- 食事の時間を一定にする(体内リズムを整える)
- 運動量を確保する(適度な運動が血流を促進し、尿の排出を助ける)
- 睡眠環境を整える(安心して休めるスペースを用意する)
- 肥満を防ぐ(過体重は尿の排出を妨げ、結石リスクを高める)
7. 定期的な健康診断を受ける
ストルバイト結石を経験した猫は、再発リスクが高いため、獣医師と連携しながら健康管理を続けることが重要です。
健康診断で確認すべきポイント
- 尿検査(尿のpHバランスや結晶の有無をチェック)
- 血液検査(腎臓機能や体内の異常を調べる)
- 超音波検査(膀胱内の結晶や結石の形成を確認)
- レントゲン検査(大きな結石ができていないか確認)
特に、治療後3?6か月間は再発のリスクが高いため、こまめに検査を受けると安心です。
8. まとめ
ストルバイト結石の予防と再発防止には、食事・水分摂取・生活環境の改善が欠かせません。日々のケアを意識しながら、猫が快適に過ごせる環境を整えましょう。
予防・管理のポイントまとめ
水分摂取を増やし、尿を薄める工夫をする
適切な食事管理を徹底し、療法食の活用を検討する
トイレ環境を清潔に保ち、猫が快適に排尿できるようにする
ストレスを減らし、リラックスできる環境を整える
定期的な尿検査と健康診断を受け、早期発見・早期対策を行う
これらの対策を継続することで、ストルバイト結石の再発リスクを下げ、愛猫が健康に過ごせるようサポートしていきましょう。
獣医師と相談しながらケアする & 定期検診の重要性
ストルバイト結石の予防と管理には、獣医師との継続的な相談が欠かせません。自己判断で食事や治療を変更すると、逆に病気を悪化させる可能性があるため、専門家の意見を取り入れながら適切なケアを行いましょう。また、定期検診を受けることで早期発見が可能となり、猫の健康維持につながります。ここでは、獣医師との連携方法と定期検診のポイントを紹介します。
1. 定期的な診察を受ける重要性
ストルバイト結石は、目に見えない段階でも進行していることがあります。定期的に診察を受けることで、早期発見と適切な対応が可能になります。
- 尿検査で結晶の有無を確認する(結石ができ始めていないかチェックする)
- 血液検査で腎臓の状態を調べる(腎臓病が進行していないか確認する)
- 超音波やレントゲン検査を活用する(目視では分からない結石の形成を発見する)
特に泌尿器系のトラブルは、初期のうちに適切な対処を行うことで、猫の負担を最小限に抑えられます。
2. 健康診断の頻度とタイミング
猫の健康状態によって、健康診断を受ける頻度は異なりますが、一般的には以下の頻度が推奨されます。
- 健康な成猫の場合:年に1回の健康診断が推奨される
- ストルバイト結石を経験した猫:半年に1回の尿検査と健康診断が理想的
- 高齢猫(7歳以上):病気のリスクが高まるため、年2回の検査が望ましい
特に、ストルバイト結石の治療を終えた後の数カ月間は、再発のリスクが高いため、こまめに検査を受けることが大切です。
3. 食事管理について獣医師と相談する
猫の体質や生活環境によって、最適なフードの選び方は異なります。獣医師と相談しながら、最適な食事管理を行いましょう。
- 療法食を継続するか、通常食に戻すか判断する
- フードの変更が必要な場合、徐々に切り替える(急な変更は体調を崩す原因になる)
- 食事のバリエーションを増やしたい場合、獣医師に適切な食材を相談する
適切な食事管理を行うことで、尿の環境を整え、結石の形成を防ぐことができます。
4. 投薬やサプリメントの使用を検討する
ストルバイト結石の管理には、療法食だけでなく、必要に応じて薬やサプリメントを活用することもあります。
- 尿のpHを調整するサプリメントを使用する(クランベリーエキスやメチオニンなど)
- 抗生剤や鎮痛剤が必要な場合、正しい投与方法を確認する(獣医師の指示に従う)
- サプリメントの効果があるか、定期的にチェックする
これらの選択肢について、獣医師と相談しながら猫の体質に合った方法を選びましょう。
5. 検査を受ける際のポイント
健康診断を効果的に活用するために、事前に準備しておくとよいポイントがあります。
- 普段の様子を記録しておく(トイレの回数や水を飲む量の変化をメモする)
- 尿を持参できる場合は新鮮なものを(病院での尿検査の精度が上がる)
- 食事内容を獣医師に伝える(療法食の効果や適切な管理方法を相談できる)
診察の際には、気になる点を事前にリストアップし、スムーズに獣医師と情報共有できるようにしておきましょう。
6. 再発時の対応についてあらかじめ確認しておく
一度ストルバイト結石を経験した猫は、再発する可能性があります。もし再発した場合の対応について、事前に獣医師と話し合っておくと安心です。
- 再発したときの初期対応を知っておく(食欲不振や排尿困難の兆候を見逃さない)
- 動物病院の診察時間や緊急対応の有無を確認する(時間外診療の対応があるか確認する)
- 治療の選択肢について理解しておく(療法食・投薬・手術などの可能性を把握する)
再発のリスクを最小限に抑えるためには、異変があった際に素早く対応できる準備を整えておくことが大切です。
7. 不安があるときは積極的に相談する
ストルバイト結石のケアには、さまざまな疑問や不安が生じることがあります。疑問点を放置せず、獣医師に相談することで、最適なケアができるようになります。
- フードやおやつの選び方が分からない場合は相談する
- 尿の色や匂いに変化があったらすぐに診察を受ける
- 体調の変化をこまめに記録し、診察時に伝える
獣医師と協力しながら適切なケアを続けることで、猫の健康を維持し、ストルバイト結石の再発を防ぐことができます。些細な変化でも相談し、猫が快適に暮らせる環境を整えましょう。
まとめ
ストルバイト結石の再発を防ぐためには、獣医師と相談しながら適切なケアを続けることが大切です。定期検診を受けることで、病気の早期発見・早期治療が可能となり、猫の負担を軽減できます。以下のポイントを意識しながら、愛猫の健康を守りましょう。
定期的な尿検査・血液検査・超音波検査を受ける
療法食やフード選びについて獣医師と相談する
適切な投薬やサプリメントを検討する
再発時の対応を事前に確認しておく
疑問や不安があればすぐに相談する
これらのポイントを押さえることで、ストルバイト結石のリスクを最小限に抑え、猫が健康に過ごせる環境を維持することができます。

猫のストルバイト結石が寿命に与える影響について総括
合わせて読みたい!
-

-
猫ストルバイト結石症の治療期間と療法食の重要性を獣医師が徹底解説
猫のストルバイト結石症の治療期間はどのくらい?症状や薬、療法食の役割、治療中に与えてよいおやつや食べてはいけないものを獣医師が詳しく解説します。ささみはOK?治った後の食生活や再発予防のポイン ...
続きを見る
